盛夏の熊本、一級建築士事務所 FU設計を共宰する梅田彰(うめだあきら)さんの元を訪れた。
梅田さんは熊本県八代市生まれで、九州東海大学の一期生。卒業後は数年間、別の会社に務めた後、大学の同級生で仕事仲間でもあった藤木一治(ふじきかずはる)さんと1991年にFU設計を設立。現在は梅田さん・藤木さんの他に、30代の秋月さん・松永さんの4人で設計にあたっている。
設立後すぐに県指定文化財の登り窯の覆屋を石場建てで建てる仕事を手掛けるなど、木造建築中心の仕事が自然と続いていった。
そんな中「古民家がどんどんなくなっていくのが寂しかった」と言う梅田さんは、せめて記録だけでも残したいとの想いで〝古民家探検団〟を作って、古民家の記録をしていく活動をしていたそうだ。

古小代の里公園 登り窯(1990)
ある日、梅田さんのもとに、古民家を4棟移築するというプロジェクトの依頼が舞い込む。まずはその仕事を紹介する。

二棟の中央にある谷樋(たにとい)が特徴的だ。今は鉄板を入れているが、当時は竹を重ねて造ったり、瓦を敷いたり様々だったらしい。
訪れたのは玉名郡和水町にある肥後民家村。各地に残る代表的な古民家を移築復元している施設で、古民家宿泊・木工・ガラス細工などの体験ができ、古人の生活に思いを馳せながら、昔暮らしが楽しめる場所だ。
今回案内してもらったのは、梅田さんが移築した4棟のうちのひとつで1765年建築の旧緒方家住宅。現在は「kinon cafe & arts」が入居しており人気を博している。残りの3棟も県内から移築してきた築150年ほどの貴重な民家だという。
一歩足を踏み入れると、店内のひんやりとした空気に古民家のならでは心地よさを感じる。実はこの日の熊本の気温は38℃!外との気温差は歴然だ。

左:移築当時の写真/右:現在入居するkinonの看板
「古い建物は使うことで活きてくるので、ここのように人が集う場所として使われるのはとてもいい事だと思います。学生を連れてきて昔の建物を見せるのにはここがいちばんいいんです。」
この建物は〝二棟造り(別棟型・分棟型と呼ばれる場合もある)〟と言われる構造で、一棟は土間、もう一棟は座敷になっている。江戸幕府の規制によって二間以上の梁間を作れなかったため、当初は小割にして別々に建てていたが、不便だったので寄せて建て、真ん中に樋を入れるようになったそうだ。南九州に広く分布していた様式だという。
熊本地震の際には和水町では震度6弱を記録。今年の1月にも和水町内を震源とする地震が発生し、その時も震度6弱を記録したが、金物を一切使用していないというこの建物が被害を受けることはなかったとのこと。

移築に当たって苦労したことを伺った。
「職人さんを探すのがとても苦労しましたね。特に茅葺をできる職人さんは県内にも数人しかいなかったので、この時は県内の他に大分からも来てもらいました。以前は茅葺をはじめ伝統構法に携わる職人さん達というのは普通にいたんですけどね。職人さんに話を聞くと彼らも『自分たちも今までは出来ていただけど、今はそういう仕事が少なく、後を継ぐ人もいない。』と言われました。だから職人さんのためにもそういう機会を増やせれたらいいなと思っています。」
そんな中明るい話題もあった。昨年、隣に建つ旧境家住宅(国指定重要文化財)の茅葺屋根の補修工事の見学会に参加した梅田さんは、阿蘇から来ていた茅葺専門の職人さんたちと知り合ったそうだ。
「若い女性の職人さんが2人も活躍されていました。実に頼もしいです。これからお願いしていこうと思っています。」
と期待を寄せている。


ベンチやオブジェなどには、お店のオーナーで国内外で活躍する木彫家・上妻利弘(こうづまとしひろ)さんの作品が使われており、古民家の個性と見事に調和している。ちなみに店長を務めているのは娘の野乃花さんだ。
梅田さんと上妻さんとの出会いはかれこれ27〜8年前にまで遡る。当時、梅田さんが建てていた道の駅のためにドアノブと看板を頼み込んで制作してもらったのが始まりで、それ以来FU設計の事務所の看板・表札・オブジェをはじめ、個人宅など様々な案件で時折家具などを作ってもらっている。
上妻さんが肥後民家村に出店すると聞いた建物が、たまたま梅田さんが移築したものだったそうだ。なんとも縁を感じる話だ。

次に紹介するのは熊本市東区にある寺院「無量山 真宗寺」の庫裏(くり:住職や家族の居住する建物の事を指す)の新築現場だ。江戸時代に建てられた庫裏に長年住まわれていたが、今回建て替えの道を選んだ。150坪で2階建てと広々とした空間が広がっている。一般的な住居に比べるとかなり大きい建物を手刻みで建てているので工務店は2社にお願いしているそうだ。
実はこのプロジェクト、木の家ネット会員でもある古川保さんとの協働案件でもある。

今から3年前の冬には、お施主さんと共に山に入り、実際に使う木を一緒に伐採する体験をしてもらったそうだ。もちろん設計もまだまだ固まる前の話だ。その理由についてこう語る。
「建て主さんには出来るだけ家づくりに参加してもらうようにしています。今はみんな『家は買うもの』と言う感覚じゃないですか。かつては『家はつくるもの』だった。うちで建てるからにはその感覚を持ってもらいたので、色々な形で参加してもらって『共につくる』ということをやれたらいいなと考えています。」

「一緒につくる事で職人さんの苦労もわかるし、どうやって自分の家が建てられていくのかも分かる。そうすればクレームではなく愛着や共感が生まれます。それから、建て主さん自身にメンテナンスの方法を理解してもらって、維持管理をしていってもらえるのも重要なポイントです。やっぱり木の家はメンテナンスが一番ですから。」

「暑さ寒さで自然を感じないといかん」という住職の想いからペアガラスは入れていない
他に建て主さん・職人さんとのやりとりで大事にしていることは何かと尋ねた。
「多くの建て主さんにとっては一生のものなので出来るだけ時間をかけるようにしています。急いでいる場合でもある程度は時間をもらうようにしています。また、職人さん・建て主さん双方と顔を合わせながらつくって行きたいので、大工さんを自社で抱えている工務店にいつも依頼しています。その上で建て主さんと相性の合いそうな工務店・職人さんを決めて、最初にその工務店・職人さんが作った家を見学してもらっています。そこで実際に住まわれている人の生の声を聞いてもらうのが一番ですね。」
梅田さんの仕事は、単に設計するという事にとどまらず、建て主・職人・家それぞれを繋ぐための糸を紡ぎ出すことなんだと感じた。



左:家具は大工さんにお願いする事が多い。「ずっと頼んでいるのでちょっとした家具屋さんに負けないぐらいになっているかな。」梅田さん 右:以前の庫裏に使われていた梁の存在が映える

3番目に紹介するのは熊本市西区上代にあるH邸。通称“上代の家”だ。
2001年に蔵を改修した後、2007年に倉庫を改修、2012年には母屋の改修を手掛けた。いずれも150年ほどの歴史を有している建物で、熊本地震の際も一部の壁が痛んだだけで、歪みなどは一切生じていないそうだ。



まずは案内してもらったは母屋。玄関をくぐると広々とした廊下と太く立派な梁が迎えてくれる。この梁がとにかく存在感を放っており、筆者は取材中何度も「梁が太い。」「梁がでかい。」と呟いてしまった。その梁についてHさんからこんな話をしてもらった。
「先代から聞いた話ですが、江戸時代には熊本城の改修のためにお城近くに貯木場があったそうです。それが明治維新でお城が必要でなくなったので、貯めておいた材木も不要になり、いろんな人の手に渡った。その中のものをうちの先代が入手して川に流して、自宅前の川で拾い上げて建てたという謂れがあるんです。」

「本当かどうか定かではないですが、家の大きさに対してこれだけ立派な木を揃える事ができたと言うのは、あながち嘘でもないのかなと思っています。守られている・包まれている感覚がありますね。」
話半分に聞いていたが見れば見るほど信憑性が増していくように思えてくる。
梅田さんも「あれと戦おうという気にはならない」と笑う。


キッチン・リビングは元々土間だったので天井が低い
梅田さんと建て主のHさんとは20年近い付き合いになるが、きっかけになったのは先に触れた上妻さん。Hさんが上妻さんのナイフカービング(木彫)教室の生徒だった縁で、上妻さんから梅田さんを紹介してもらったそうだ。家の中にも上妻さん作の家具が並んでいる。




テーブルとイスは上妻さんに作ってもらったもの。テーブルは改修前の家で上がり框だった桜の木を使用している。
熊本地震で一部剥がれた壁の修復を左官さんにお願いしたところ「どうせやるならとことんやらせて欲しい」と申し出があり、部屋ごとに全て違う素材で仕上げられている。左官さん1人での作業だったので1年の手間暇を費やしたという。壁一つで部屋の雰囲気がガラッと変わってとても面白い。




左上:玄関左手の“下の間”は黒い砂鉄壁。塗る時に垂れてきて大変だそうだ。/右上:この赤い土は今では採れないものとのこと。
左下:こちらは砂を混ぜている。/右下:だんだん白くなるという土佐漆喰と真っ黒な梁のコントラストが美しい。
梅田さん・左官さん・上妻さんをはじめ、家づくりに携わったつくり手側の意気込みもさることながら、これだけこだわったディテールにできるのは建て主であるHさんのものづくりに対する深い理解があるからこそだろう。Hさんはこう言う。
「この辺りでも戦前からの建物が何軒かあったんですが、今では一軒もなくなってしまいました。これは逆に残しておかないといけないなと気合いが入りました。古い家にはそれぞれの歴史があるので、みなさん残したいという気持ちはあると思うんです。でも、いざ改修しようという話になった時に、梅田さんのような設計してくれる人・施工してくれる人・環境・タイミングなど、何拍子も揃わなければ実現できないと思います。」

「見た目は和風でも新建材を使った“なんちゃって”が多いですよね。そういったものは出来た時が100%であとは朽ちていくだけですが、昔ながらの自然素材の家はだんだん味が出て育っていくのが魅力ですね。」

次に2001年に改修した蔵と2007年に改修した倉庫を案内してもらった。蔵はただの物置になっていたので、そのまま直すのではお金や手間暇をかける意味があまりないと考え、来客時や一人の時間を楽しむための空間として生まれ変わらせている。まさに“男の住処”と呼ぶにふさわしい風情があり、非日常を楽しんでいるそうだ。外壁のなまこ壁は今年から左官さんに改修をお願いしている。
桁から下は健全だったので屋根は新調したが、その他はお金をあまりかけずに、目に見えるところはしっかり作られている。

稲穂を埋め込んだ壁が目を引く

左:ここにも上妻さんのテーブルとイスが並ぶ/右:モダンなトイレに遊び心が感じられる



左:改修前の蔵の外壁につけられていた飾り/中・右:改修中のなまこ壁。
倉庫は元々他のところから移築されたもので、建物自体は母屋や蔵よりももっと古いものだ。傾いてしまっていたので、2007年の改修では基礎を入れている。外壁・内壁共に職人技が光る。

倉庫壁面の腰から下には蔵に乗っていた“目板瓦”を貼ってある。今ではもう作られていない。


左:壁面に強い風雨がかかるのを避け、漆喰の壁を白く保つ“水切り瓦”/右:削り漆喰の壁:今年の地震で剥がれたのはこの2面だけ
内壁は「削り漆喰」で、下地の小舞を竹ではなく板の桟で組んでおり、隙間に漆喰が入り込むので粘り強く、力を吸収してくれるという。土に関しては蔵の屋根などから集めたものを使用している。その時の左官さんがこんな事を語っていたそうだ。
「左官の仕事というのは普段は仕上げしか見られない。何十年か経って壊したり修復したりする時に初めてその左官の仕事がどうだったかを判断される。その時に『きちんとした仕事だな』と思ってもらえるような仕事をしないといけない。」
その姿勢にHさんもたいそう関心したそうだ。地震で一部剥がれてしまったので“その時”が来た訳だが、今、蔵と倉庫の改修にあたっている左官さんは、実は最初の改修時の左官さんの元お弟子さんとのことで、ここでも縁や繋がりを感じる。
梅田さんが「そこで実際に住まわれている人の生の声を聞いてもらうのが一番」と言う通り、Hさんから聞く話はとても興味深く、梅田さんとの信頼関係もよく伝わってくる。

20年近い関係を築いている二人からは親密な空気が感じられた。
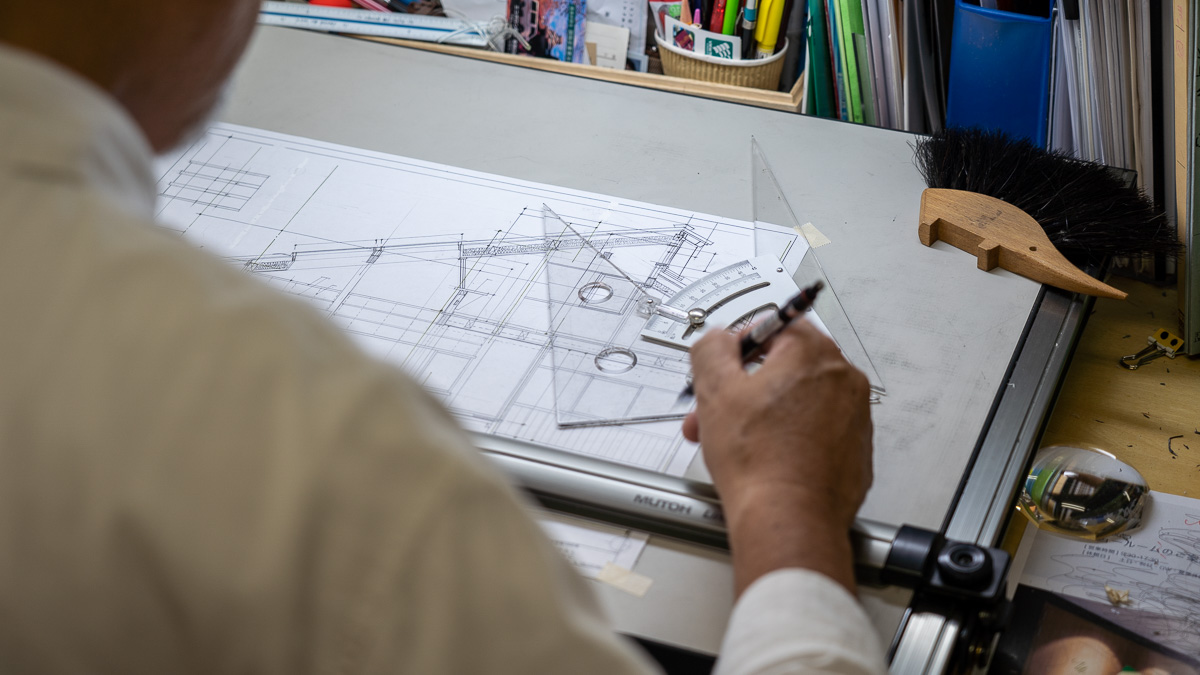
今も手描きで図面を引いている。「決め切らない曖昧なところがいい。」
梅田さんの会社 FU設計が入居している「EL SOCIO BILD.」は、1990年にFU設計の他に司法書士・社会保険労務士・税理士それぞれの知り合いを集めて、みんなでで土地を借りて建て、共同で管理しているそうだ。もちろん設計はFU設計(藤木さん)だ。このビルには共有の会議室があったり、廊下がギャラリーとして使えたり、ライブラリー(今は間貸ししている)があったりと、開かれた場所になっており、昔はPTAの会議などにも使われていたそうだ。
「地域の子供たちが集まってきてくれるような場所になればいいなと思ってスタートしたんです。」

「一番家づくりで大切なのはコミュニティだと考えています。環境を作ってあげるということで、家族の住環境ということだけではなく、地域の人との関係をどう育んでいけるか。家を建てて終わりではなく、どうやって地域の人と仲良くできるかという“仕掛け”を作れたらいいなと思っています。隣近所の人が集まって来て楽しく酒を飲めるような環境を、生活してゆくなかで作れるのが一番いいんじゃないでしょうか。会社や学校と家との往復だけで、隣近所の人と挨拶も交わさなかったり、仕事をリタイヤしたあと一人で家に閉じこもっていたりするのは寂しいじゃないですか。」

事務所の廊下にて:左から梅田さん・秋月さん・松永さん・藤木さん。実は梅田さんと藤木さんは誕生日が一緒だそうだ。ここでも縁を感じる。
梅田さんの日々の仕事には、家づくり・コミュニティづくりに対するこうした考えが根底にある。人との縁・人間関係を大切に育みながら今日も図面を引いている。
取材・執筆・写真:岡野康史 (OKAY DESIGNING)
土と水とわら。素朴な自然を混ぜ合わせ美しい空間に仕上げる左官仕事を、愛してやまない職人がいる。三重県四日市市の松木憲司(まつき・けんじ)さんだ。15歳から左官一筋。住宅から蔵、文化財までいくつもの壁を、本物の素材にこだわって塗り上げ続けてきた。
「時代が変わっても、いいものは変わらない。だから自分はぶれずに、左官仕事はいいって言い続ける」という信念で、イタリアなど海外にも出展し、その技術を世界に認められている。
それでもさらに、「蒼築舎(そうちくしゃ)」を立ち上げ次世代の育成や近代建築との融合など、新しい分野に飛び込む姿は、まさに挑戦者だ。
松木さんは、三重県四日市市の親方のもとで5年修行。親方は友人の父親だったため、軽い気持ちで飛び込んだ世界だったが、「自然素材を扱うからとにかく気持ちがよくて。形のないもん(土や水)を形にしていくのも、難しいけどたまらなく楽しかった。性格が合ってたんだろうな」と、あっという間にのめりこんだ。

使い込まれた愛用の手道具たち
21歳で独立後は、地元の左官職として、竹小舞下地、塗り壁など施工してきた。ところが30歳手前のころ、建築業界も変わり始めた。それまで主に松木さんが手がけてきたのは伝統構法だったが、効率化を重視した大量生産の住宅が台頭し、「土壁塗りの仕事がピタッとなくなった」(松木さん)時代だ。タイルやブロック貼りの仕事をしながら、やりたい仕事ができないことに思い悩む日々だったという。
松木さんはもんもんとした思いを、大津磨きなど技術向上にぶつけてきた。33歳の時には、全国左官技能大会で優勝するまでの実力を身に着けた。その縁で、ドイツ、イタリア、タイ、ベトナム、フランスなど海外でのプロジェクトに参加するようになる。海外経験は皆無で、言葉も不自由な松木さんを後押ししたのは、「日本の技術を見せつけてやる」という情熱だった。
実際に訪れたヨーロッパの壁は、日干し煉瓦を積み上げる、「版築」という土を突き固める、などが主流で、「日本の”塗る”左官技術にはみんなもうびっくりして、喜んでくれた」と手ごたえを得た。

海外での土壁塗りは大好評
以来、竹木舞と土壁、得意の大津磨きなど、自然素材を使った「自分がいいと思える仕事をしたいと声に出して言うようになった。そうすると、不思議とそういう仕事が集まってきた」と松木さん。自然素材と伝統の技にほれ込み、信じ、こつこつと積み重ねてきた仕事ぶりが、縁を繋いできたのだ。

現在は、ひと月に多ければ5、6件の現場をかけ持つ多忙ぶり。東海エリアを中心に、関東での出張仕事もこなす。
そして、どの現場でも、市販のプレミックス材ではなく、土と砂と水、すさなどの自然素材を調合して壁を仕上げる。「こんな現場、他にはないでしょう」と誇らしげだ。

愛知県常滑市の新築物件では、内壁を荒壁を塗った後、大直しの「ざっくりした状態」(松木さん)で仕上げる。大直し用の材料は、荒壁に使ったものに土やすさを加えて練り直して作る。

調合を担当するのは、息子の一真さん。足で練った後、ミキサーで混ぜて仕上げる。感触を確かめながら、微調整を繰り返す。
自然素材でやることこそ、「本物の左官の仕事だと思っている」と強調する松木さん。
その理由は3つある。1つは、ごみが出ないこと。壁塗りは、1日に必要な量を予想して午前中に材料を作る段取りで仕事をしている。プレミックス材は、その日に使いきれなかった場合、ただごみになってしまうというが、自然素材なら使い切れずとも翌日に練り直せばいい。家を解体した時の古い土も、練り直せばまた使える。使わなかったとしても、置いておけば自然に還ると考える。「今はゼロ・エミッションとかサステイナブルとか、気取った言葉が流行っているけど、左官はずっと昔からそれをやってきた」という。

常滑市の現場近くに崩れた土壁の家を見つけた松木さん。「土に還るってこういうことだ」と語る
2つ目は、自然素材ならその建物にぴったり合った壁を作れること。新築か、古材を移築した現場か、はたまたその折衷か、同じ現場は一つもないという松木さん。「例えば、年季の入った飴色の古材に、真っ白ぴかぴかの漆喰じゃ落ち着かないやろ。自分で調合すれば、土の種類や色、割合を変えて、その空間に一番合った壁を作れる」と自信を見せる。プレミックス材もバリエーションはあるものの「自分で混ぜた時の自由さには適わない」と考えている。

どんな素材をどのように混ぜ合わせるかによって、壁の表情は多彩になる

常滑の現場では、玄関の壁に施主さんの子どもが海岸で拾ってきた小石を埋め込んだ。憎い演出だ
そして3つ目は、「難しいことができてこそ、職人」という志からだ。ただ規定量の水を加えるプレミックス材と違い、自然素材の調合では、その日の気温や湿度、壁の陰ひなたによって、微妙な調整が必要になる。練っている時と壁に塗った時、乾いた時の色味が変化するため、それも換算しなければいけない。「考えること、自然を感じること、それから、場数が必要。簡単には身につかんよ。だから、日曜大工はいるけど、日曜左官はいないやろ」と松木さん。左官職人としてのプライドがにじみ出た。
そうして作り上げた空間は「無理がなく、気持ちいいし、時間が経てば経つほどよくなる」。施主さんに、家族団らんで穏やかな暮らしを提供している。
松木さんは、独立後「松木左官店」という屋号で活動していたが、2002年には「蒼築舎」に変更した。後継者を育成していこうという思いを込めた。門戸を叩いた人は断らない主義で、これまで10人の弟子を受け入れた。現在は左官歴9年の一真さんと、20代の落合綾香さん2人が腕を磨いている。

弟子といっても松木さんにとっては、「一緒に仕事をする仲間」という存在だ。
修行時代から「左官は共同作業」という思いがあった。壁塗りは材料の性質上、水が引く前に一気に仕上げる、時間との勝負だ。特に、大きな壁になるほどその傾向は強くなる。
「仲間の存在は、より精度の早いものをスピーディーに作れるという安心感がある。それに、自分の腕自慢をしたって、施主さんは喜ばない」と語る。
弟子は基本的にはどんな現場も同行させ、自分の仕事ぶりを見せるとともに、やり方を教えてどんどん場数を踏ませる。言葉で説明することもあれば実際に手を動かして教えることもあるし、最近はスマホで動画撮影もしている。
名古屋市の古民家移築現場でも、弟子とともに3人で漆喰を塗りながら、松木さんは「そこはこうやってしておいてくれる?」「ここは絶対汚すなよ」と的確な指示を出すとともに、「うん、いいね。うまいうまい」と、丁寧に言葉をかけていた。落合さんは修行歴1年。指導については「教え方はわかりやすい。見て覚えろ、というタイプではないです」と話す。

松木さんは「うまくできなければ壊してやり直させる。声を荒げて怒ることもある」と言いつつも、「最近の若い子
は丁寧に仕事してくれる。それに、前は教えるってことは失敗させることやと思っていたけど、だんだん、それなら説明せなとなったな」と自らの変化も実感する。
息子であり弟子でもある一真さんは「親方はやっぱり土のことよくわかってる。一緒に仕事して、毎日、何かしら達成感と学びがある。楽しいです」と、左官仕事に魅了されている。
ぶれない松木さんのスタイルは、今、新展開を迎えている。
これまでの現場は、伝統工法や古民家改修、社寺建築などいわゆる日本らしいものが主流だった。今年の夏、コンク
リートと土壁を融合した新築物件という初めてのジャンルに挑戦したのだ。
きっかけは、講師を務めている愛知産業大学での出会いだ。左官仕事や自然素材の魅力を語る松木さんの話を「もっと聞きたい」という教授や建築士が、有志で親睦を深めていった。ついには、土の建築物をもっと研究しようと「土左研(どさけん)」という集まりが立ち上がった。
メンバーの一人の浅井さんは、これまでは店舗設計などコンクリートを多用した近代建築を手掛けることが多かったというが、「松木さんに出会って、土壁という自然に還るものの美しさに気づかされた。今の時代に求められているものだと思う」と話す。

現場で盛り上がる松木さんと浅井代表
時を同じくして常滑市の海に近い新築物件を手掛けることになり、津波対策を考えつつ自然素材も取り入れたいという施主さんに、土壁を提案した。設計した物件は、家の中心となるキッチンとリビングの壁はコンクリート製で、その周囲に子供部屋、寝室、浴室などを配置する。周囲の部屋の壁を、土壁の大直しで仕上げるという、独特のスタイルだ。

(写真提供:トロロハウス)

無機質なコンクリートとぬくもりのある土壁の調和に「今まで見たことない、スタイリッシュな空間」と松木さん
浅井代表いわく、津波がきた場合、土壁部分は流されるがコンクリート部分は残るような仕掛けになっている。外壁は焼杉仕上げで、流された土壁や構造材は土に還る。
それから、海風が強い地域のため外側の壁が傷み、変化が出てくるが、土壁ならその変化すら楽しめると考える。痛みがひどければ直すこともできる。もし子供が独立して部屋が不要になったら、壊してしまっても土に還る。安全を確保しつつ、暮らしながら変化を楽しむ家、というコンセプトだという。
2人を含む「土左研」メンバーの願いは、「左官の技術を次の世代に残したい。そのためには、伝統建築だけにこだわらず左官の活躍の場を広げたい」ということだ。
「真行草」という言葉がある。発端は書道の言葉で、いわば本来の楷書の形(真)から、少しくずした「行」書、そして、さらにくずした「草」書がある。それぞれにそれぞれの美しさが存在するという意味で、松木さんは新しい挑戦をする時に思い出すという。

異素材との組み合わせで、土壁がまた違った輝きを魅せる
松木さんは語る。「メンバーで、酒飲みながら生まれるアイデアは、俺1人じゃ考えつかない。仲間がいることで世界が広がるし、そのアイデアに左官としてどう応えようか、って考えるとわくわくする」。
挑戦の原動力は、左官仕事の魅力を誰よりも知り、信じる熱い情熱だった。
取材で訪れた漆喰塗りの現場。松木さんと弟子2人が、するりするりと土を壁に重ね、なめらかに整えていく。
松木さんには「塗りながらでも話せるから、何でも聞いて」と言われたものの、私は目を奪われ、ろくに質問もできなかった。あまりに美しく、何か上質な映画を観ているようだった。
「土左研」メンバーの浅井さんも「松木さんの仕事って、すごく始末がいいよね。見ていて気持ちがいい」と話していた。
鏝(こて)を動かす腕から、壁を見つめるまなざしから、職人の気迫や伝統の重み、自然素材の力強さなど、言い尽くせないたくさんのものが伝わってくるのだ。
もっとたくさんの人が現場を見て、職人技に触れてほしい。「木の家を選ぶ人は少ない」「職人は減少するばかり」という課題も、この仕事ぶりを見れば解決してしまう、と思わせるかっこよさだった。
取材・執筆・撮影:丹羽智佳子/写真の一部は蒼築舎、トロロハウスに提供いただきました
梅雨の合間のよく晴れた日、「あゆみ大工」の坪内一雅(つぼうちかずまさ)さんの元を訪れた。場所は長野県南信州・上伊那郡中川村。新緑と田植えの水面が輝き、日本の原風景が広がる自然豊かな土地だ。

山脈に囲まれた一面の田園風景。坪内さんの田んぼでも田植えをしていた。
坪内さんは愛知県出身で県内の大学を卒業し、設計事務所に3年間務めた後、品川の技専で木工を学ぶ。「デスクワークよりも現場の方に魅力を感じた」という坪内さんは、やるからには日本の伝統的な建て方をしているところで働きたいと思い、名棟梁・田中文男さんのもとで5年間修行を積む。その後いくつかの会社で経験を重ねた後、長女が小6の時に一念発起。母親が暮らす長野へ移り住んだそうだ。

「このタイミングを逃すとずっと親の面倒を見れなくなるので。もちろん不安もあったんですが、伊那には大工塾の同期の知人がいたり、応援してくれる人もいたので後押しになりました。」
そう振り返る坪内さんだが、今では地元で「あゆみさん」と慕われ、とても忙しく仕事をしている。「あゆみ大工」という屋号になった所以が気になったので尋ねてみた。
「大工になる前から“歩くこと”に縁があり、仕事をする上でも走るのではなく、一歩一歩歩んでいきたいと思ったんです。また漢字で“歩み”と書くよりも、ひらがなの“あゆみ”と書く方が優しい感じがします。この読みにはこの漢字と言う風に、枠に嵌めて決め込んだり、何かに執着するのは自分の感覚とは違うなと思っています。「いいかげん」ではなく「良い加減」と言うのが私のモットーなんです。あまり執着すると生き方に壁を作っちゃうなぁと思い、伝統的なものだけにこだわり過ぎず、いろんなことをやっています。その方が〝とんち〟が効くんです。」


左:奥さんが田植えをしている最中だった 右:除草のために借りている「レンタルやぎ」
「良い加減」で、とんちを効かせながら仕事をされる坪内さん。その仕事ぶりがわかるセルフリノベーションの事例を紹介する。

訪れたのは、伊那市東春近にあるSさんのお宅。小さく見えていたむくり屋根が、車で近づくに連れて徐々に大きく見えてきて、期待も膨らむ。ここは元々茅葺き屋根だった築150年の由緒ある古民家をSさんが2012年に取得した物件で、坪内さんはよろび起こし(傾きを直すこと)や根継ぎ(柱や土台の腐った部分を取り除き、新しい木で継ぎ足すこと)、屋根の補修など、建物として維持させるための改修を担当し、内装の造作などは施主のSさん自身が少しずつセルフリノベーションで改修しながら暮らしている。ちなみに土壁はSさんがワークショップを開催して一般の方と一緒に仕上げたそうで、そういった家の改修や伊那谷での生活の様子をブログ「伊那谷の古民家再生」で公開しており人気を博しているそうだ。



左:改修前の茅葺き屋根の様子(写真はSさん提供) 中:元々の茅葺き屋根を新しい屋根が覆っている 右:改修した屋根の間を覗くと当時の状態がそのまま分かる
改修前はいたるところが朽ち、屋根にいたっては茅が腐って落ちてしまっている場所もあったので、雨漏りがしていたり、柱が腐っていたりと、とてもそのままでは住めるような状態ではなかったという。改修にあたり、何件か他の大工さんにも声をかけたが、目に入った瞬間に「やめておいた方がいい」と言われたとのこと。そんな中、坪内さんは土間の立派な梁を見て「いや、絶対直るし綺麗になるよ。やりましょう!」と改修を勧めたそうだ。

「雨漏りや歪みの問題、住んでいた人の考え、環境の変化など、様々な要因によって倒されてしまう家があります。中にはここのような素晴らしい立派な建物がいっぱある。その家を自分が関わることによって救うことができれば、『よかったなぁ』と純粋にうれしいです。お金に換えられえない達成感があります。」
そんな想いで取り組んだS邸の仕事で一番心に残っているのはどこなのか尋ねたところ、一番大変で、且つ一番やりがいがあったという屋根の改修について語ってくれた。


新しい屋根の下から茅葺き屋根が顔を覗かせる
「この屋根を合理的に直すなら茅葺き屋根を取っ払って普通の屋根にすれば良いのですが、せっかくの貴重な建物ですので、元の面影を残す形で「むくらせたいな」と思いました。なるべくお金をかけずにできる方法はないかといろんな人に聞いて回って、「むくり屋根」の再現を試みました。特に大変だったのは、雨漏りで材の仕口(柱や梁の接合部)が腐って失くなっている箇所の修復ですね。エポシキ樹脂の接着剤と5㎜角の材木を集成し、接着材が乾いたら整形するという工程を2~3回繰り返して形にしました。また軒先が垂れている部分は桔木(はねぎ:屋根裏に取り付ける材で、テコの原理を利用して軒先をはね上げるようにして支える)を入れて直しました。イメージ通りふんわりした印象に仕上がり、手間をかけた甲斐がありました。」
坪内さんは「家を救いたい」そして「家を救おうとしているお施主さんの手助けをしたい」という想いを胸に、心を込めてセルフリノベーション・セルフビルドの仕事をしている。



腐っていた柱は根継ぎし、さらに添え木をするなどして修復している



左:石場建ての間にモルタル・ワラ・土を混ぜたものを入れている 中:Sさん自身で塗ったいう「拭き漆」 右:室内の造作に名家の面影が残る

次に紹介するのは駒ヶ根市赤穂にあるM夫妻所有の住宅。こちらのもセルフリノベーションにて絶賛改修中だ。M夫妻の自宅横で奥さんのおじいさんが住まわれていた明治時代のもので、改修後は民泊として貸し出す予定になっている。坪内さんとM夫妻が3人揃って作業に当たるのは週に2日。その日に技術的なことをレクチャーしたり、疑問点を解決したり、相談したり、コミュニケーションを取りながら作業を進め、残りの日はM夫妻のペースでじっくりと作り上げていっている。

笑顔の絶えない現場でのやりとり
「中には『大工の作品に素人の手が入るなんて邪道だ』とお叱りになる方もいるかもしれないですが、家というものは自分の作品である前に、お施主さんのものなので、ご本人に家に対して愛着を持ってもらいたい。その方法として楽しんで創り上げてゆく参加型の家づくりはベストだと思っています。」
そう断言する坪内さん。M夫妻との笑顔の絶えないやりとりを見ていると、「確かにそうだ」と納得した。

建てられた当時から残る土壁の下地には「竹小舞」ではなく、葦を束ねた「葦小舞」が使われていた



左:Mさんのアイデアでコーヒーガラを入れた漆喰
中:床にはサクラ・ケヤキ・アカマツ・カラマツ・クリ・ツガ(トガ)の6種の木を使用/写真はMさん提供
右:通常のストーブではなくペチカを設置している

「人との関係を大切にしたい」という坪内さん。着実に素晴らしい関係を築いている。

最後に紹介するのは、電子部品などを製造しているK社さんにて、異業種の人たちと共に進めている実験的なプロジェクトだ。間伐材を使ったビニールハウスで、鉄の柱よりも木の柱の方が作物の育成に良いのだとか。あまり詳しくは語れないが「今後の展開に乞うご期待」とのことだ。


伝統的な日本家屋の仕事だけに執われることなく、どんどん新しいことにチャレンジしている坪内さん。伝統をしっかりと学び経験を積んできたからこそ、新しいことに対しても「とんち」を効かせた柔軟な発想で向き合うことができるのではないだろうか。

いつも朗らかな坪内さんだが、会話が弾み建築業界の話題に話が及んだ時、笑顔の合間に真剣な眼差しを垣間見る瞬間があった。
「引っ越して来たばかりの時は当然仕事もなかったので、ハウスメーカーの仕事も手掛けていたんですが、やってみてやっぱり面白くないんですよね。『こんなことをやるために大工になったんじゃない』と思い8ヶ月ほどで辞めました。でもいろんな想いを胸にやっている人がいます。組立工と化していて数をこなさなければならず、暇もなく骨身を削り頑張っているんです。それを喜びに変えるには相当なモチベーションが必要だと察します。日本の建築はおかしいぞと感じますね。」
「もっとおかしいなと思っているのはプレカット。在来工法でプレカットと手刻みで相見積もりを取られたら、普通のお客さんはやっぱりプレカットを選択しますよね。そりゃ安い方がいいに決まってますから。見積もりを並べられて『この金額で削れるか』みたいな話になっちゃう。そこはどうにかならないものかと思います。例えば行政から助成金が出るとか、何かしら職人を残していく方法が必要だと考えています。やっぱり大工というものは、実際に刻まないといろんなことがわからない。手で刻んだか刻んでいないかで建前の意気込みも全く違うはずです。」

さらに続ける表情に、またいつもの柔らかい笑顔が現れた。
「一方で、もちろん価値をわかってくれる人も必ずいるので、そういう『ぜひ刻みで建ててください』というお施主さんを捕まえなきゃいけないなとも思ってます。まだ自分がそういうステージに上がれていないのかもしれないので、世の中を悪く言うんじゃなくて、自分のことをよく見なきゃいけないですね。『いい年でそろそろ定年なのによく言うね』みたいな声も聞こえてきそうだけど『いや、まだまだこれからだよ』という意識もあります。」
坪内さんの言う「良い加減」とは物事を真剣に見つめ、そこにある理想と現実を把握してどちらかに寄り過ぎることなく、地に足をつけて一つずつきちんと解決して行くことだと感じた。そこが坪内さんの魅力であり、あゆみ大工の魅力なのだろう。
坪内さんは今日も一歩一歩、長野の地を踏みしめながら大工という仕事に向き合っている。
取材・執筆・写真:岡野康史(OKAY DESIGNING)